錯誤を始めて勉強したときは簡単だなと思っていたのですが、
最近ローで授業を受けてからというもの、なんだか難しいなと感じるようになりました。
そういうわけで、ローで学んだ「基礎事情錯誤」の内容を共有して、自分の中の頭を整理したいと思います。
認識が「真実」に反する
「日当たりの良いマンションかと思ったら、そうではなかった」という誤解を、基礎事情の錯誤と言うためには?
基礎事情の錯誤取消(民法95条1項2号)の要件は
①法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反すること
②錯誤が重要なものであること
③基礎事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていること
④錯誤に基づき意思表示をしたこと
⑤取り消しの意思表示
だと学びました。
さて、基礎事情の錯誤と言うためには、まず①の要件を満たす必要があるわけですが、良好な日照が得られると思って購入したマンションの一部屋が、案外そうでもなかった場合に、
「良い日照」という基礎事情と、「悪い日照」という真実とでは
食い違いがある!
と言えるのでしょうか。
良し悪しなんてものは、評価です。
人によって違うのです。主観的なものです。
真実というのは、客観的なものです。誰が見ても「その通りだ!」と言えなければなりません。
では、良し悪し、ではなく、有る無し、ならどうでしょうか。
「日差しを遮る建造物が無い」という事情と、「日差しを遮る建造物がある」という真実とでは食い違いがある!
と言えるでしょうか。
建造物の有無は、誰が見てもわかります。
なので、基礎事情の錯誤を論述するとき、日照が良いと聞いていたのにそうでもなかったという事案、カッコイイと思って買ったフィギュアが不細工だったという事案などでは、
良し悪しではなく、有る無しに置き換えて基礎事情と真実の食い違いを説明する必要がありそうです。
錯誤はリスクの転嫁
「真実を知っていたならば意思表示しなかった」なら、いつでも錯誤は重要と言っていいのでしょうか。
普通、私たちは物を購入するとき、その物の定価や効用なんかを気にします。
それは高額な商品になればなるほど慎重に判断するものです。
本来、情報収集は表意者側がしっかりと行って、これに基づいて購入の意思表示をする(あるいはしない)のが筋です。
なので、思ってたんと違う!、となっても、それは情報収集の懈怠。
表意者が泣くべきなのが原則です。
ところが、民法は、こうした錯誤に陥った場合であっても契約をなかったことにできるわけですよね。
本来、表意者側が泣くべきであったところ、契約を無しにすることで相手方に泣いてもらう。
そのリスク転嫁を可能にするのが、②錯誤の重要性や③基礎事情の表示、の要件なわけです。
なので、契約の内容や当事者の属性に応じて、表意者側に要求すべき情報収集努力義務の有無や程度、
つまり、本来は表意者が泣くベきところを相手方に泣かせるのが妥当か、という観点
に思いを致しながら、②③を当てはめていくべきとのこと。
確かに、錯誤の重要性(②)を表意者の立場に置かれた一般人を基準にしているのも、その趣旨なのかもしれませんね。
では、具体的な設例から考えてみます。
今日は金が1g当たり10000円の取引相場。Aさんはこれ以上の下落を恐れて金を売りに行きます。店に行ってみると、貴金属店長Bは、1g当たり11000円で買い取ると言う。ああ、これは昨日の金相場と勘違いしているなとAさんは思うが、黙っておくことにした。このとき、果たしてBさんの錯誤は基礎事情の錯誤と言えるでしょうか?
Bさんが金をAから買い取ったその基礎事情は、今日の金相場が1g当たり11000円であるという事情です。
しかし、本当の相場は10000円ですから、Bさんの認識は真実に反しています。(①充足)
先に、③基礎事情が表示されていた、と言えるか見てみると、
Bさんが11000円で買い取ると言ってますから基礎事情は意思表示を構成していますし、
Aさんとしても店の人がそう言うなら、ということで契約に入っているので、法律行為の内容になっていると言えるでしょう。
この結論を動かすことはできなそうです。
では、②錯誤の重要性、はどうでしょうか。
やはり貴金属店である以上、金相場は日々チェックするべき立場であるBさん。
情報収集をすべき努力義務はB店長に高く要求されているというべきです。
よって、高く買い取ってしまうというリスクは、情報収集努力義務を負うB店長が背負い込むべき。
そういった私達の感覚をどうやって法律論に持ち込むかと言えば、
「法律行為の目的及び取引上の社会通念」
でしょう。
よって、錯誤の重要性は満たされないという結論になります。
お陰様で、リスクを客Aに転嫁せずに済みました。
(重)過失の水準
さて、過失というのは規範的なもの。
なので、過失かそうではないかを分ける基準線は、事案によって異なるとのこと。
Bさんは貴金属店長なのですし、金相場を確認するのは基本ですよね。
これを怠ったのですから、重過失と言っても良さげです。
では、Bは確かに金相場を誤解して1g当たり11000円で買い取ったものの、将来金相場は1g当たり15000円まで上がり、そこで落ち着くと確信していたならどうでしょうか。
Bさんにしてみれば、ここ最近下落気味である昨日今日の金相場など、些細な問題かもしれません。そこに注意を払うべきであったとまでは言えない。
するとBさんが払うべき注意義務は、そもそも無い。よって、重過失は存在しないから取消はできないという結論になりそうです。
このように、人や目的などによって、重過失の水準は変化するということを、忘れないようにしたいと思った私でした。
さいごに、重過失の定義を共有しておきます。
95条3項柱書における重過失とは、表意者の職業、行為の種類、目的などに応じ、普通になすべき注意を著しく欠いていること、を言う。
以 上

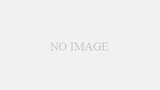
コメント