ロースクールで行われた民事訴訟法の授業を基に書きました。
以下、本編。
訴え・請求・訴訟物の言葉の意味と関係性
訴え、訴訟上の請求、訴訟物、という言葉は、民訴法を勉強していればよく耳にすることと思いますが、今回は、これらの言葉の意味と関係性について、授業で学んできたので共有したいです。
訴えとは、原告が裁判所に対して特定の権利または法律関係の主張を提示し、これに基づいて判決を求めることを言います。
請求とは、原告が被告に対してする一定の権利主張です(狭義)。
訴訟物(狭義)は、請求(狭義)と同じ意味です。
これら言葉の意味を列挙したところでって感じですが、つまり言いたいことは、
裁判で争いの対象となる訴訟物は、原告のする請求によって決定されるということですね。
裁判所が勝手に訴訟物を設定してみちゃったりすることはできないのです。
そして、「訴え」と「請求=訴訟物」の違いは、相手方が裁判所か、それとも被告なのかということ。
つまり、対象が異なるのですね。
だからこそ、訴えを退けることを「却下」と言い、請求を退けることを「棄却」と名付けることで区別しているわけですな。
教授曰く、ある時テレビを見ていると、コメンテーターが「訴え棄却」だったか「請求却下」だったかという用語を使っていたそう。
裁判所の視点
訴えと請求・訴訟物の違いは、対象が裁判所なのか被告なのかにあると言いましたが、どうしても訴訟法を勉強していると、当事者の関係ばかりに目がいってしまうのは僕だけでしょうか。
既判力は事実審口頭弁論終結時を基準時としている(民事執行法35条2項)わけですけれど、その実質的な理由は何でしょうか。
私なら、「事実審口頭弁論終結時までは当事者はお互いに攻撃防御を展開できるため、その時までを判断資料に入れても当事者にとって不意打ちにはならない」みたいな説明を最初に頭に思い浮かべます。
ただ、訴訟は裁判所も関わってくるもの。
裁判所の視点から見た理由付けも考えておくべきなのです。
これも今日の授業で気づかされたことです。
例えば、「事実審口頭弁論終結時までは当事者が訴訟資料を提出できるから、その時までを裁判所は判断資料に入れるべきだから」みたいな説明になるでしょうか。
以 上

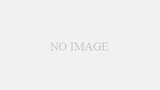
コメント