ロースクールに通っていると聞こえてくる生徒の声が、「文提は出ない」です。
一コマを割いて授業する割に、ロー生の評価としては文提は軽んじられやすい傾向にあるみたい。
だからこそ、文書提出義務を極めておけば、司法試験で一線を画する答案を書くことができるようになるでしょう!
さて、今回はローの授業で文書提出義務を勉強した上で、特に自己利用文書について気を付けようと思ったことをいくつか共有してみたいと思います。
団体のプライバシー?
専自己利用文書(220条4号ニ)に当たるための要件は、①専ら内部利用目的で作成され外部開示の予定がなく(内部性)、②開示すれば個人のプライバシーや個人または団体の意思形成に看過できない不利益が生ずる場合(不利益性)であって、これらに当たる場合であっても、開示すべき③特段の事情がない場合を言うと解されていますね。
不利益性の要件を判断するにあっては、プライバシーという権利に不利益が生じているかどうかを判断することになるわけですが、ここで気を付けることは、プライバシーの主体に団体は含まれていないということです。
ですから、当該文書が開示されることで団体Xのプライバシーが侵害されるので②を満たす、などと書いてしまってはいけない。
特段の事情に何を容れるか
開示すべき③特段の事情がない場合、に言う「特段の事情」って何でしょうか。
これについて八王子信用金庫事件(最決平成12年12月14日)の事案を見てみましょう。
信用金庫Xの会員であるYは、Xの理事の責任を追及する会員代表訴訟を提起した。その訴訟の中で、理事の責任を明らかにするために、X作成の融資に際して作成された稟議書と意見書の提出命令を申し立てた事案です。
判例は、開示すべき「特段の事情」があるかを判断する際に、申立人(Y)が文書の利用関係において文書の所持者(X)と同一視することができるかという観点から判断しました。
つまり、申立人=文書の所持者、と言える時は、開示すべきということになります。
本件では、信用金庫法が会員の会計帳簿閲覧謄写請求権を認めていないこと、会員代表訴訟は理事の責任を追及することができるにすぎず、これを提起することができるからと言って信用金庫と同一の立場で文書を利用することができるとまでは言えないことを理由に、「特段の事情」を認めませんでした。
では、「特段の事情」というのは申立人=提出義務者の場合だけでしょうか?
これについては、決して「特段の事情」というのは申立人=提出義務者と同視できる場合に限られないとした判例(木津信用組合事件 最決平成13年12月7日)があります。
この事案は、経営破綻したA信用組合の営業の全部を譲り受けた整理回収機構Xに対して、A作成の貸出稟議書の提出命令をAの債権者らが申し立てた事案です。
判例は、A信用組合はすでに営業をXに譲渡しており、清算中でもあるために、貸付業務を行う予定がないのであるから、A作成の貸出稟議書をXが提出したところで、団体Xの意思形成過程に看過しがたい不利益が生ずるおそれはないとして、開示すべき「特段の事情」があると認定されたものです。
上記の事情は②の不利益性で判断すべきことであったようにも思われますが、とにもかくにも、「特段の事情」というのは、所持者=申立人という、八王子信用金庫の示した場合に限られるということはない、と最高裁は考えていると言えそうです。
では、さらに話を進めて、文書を証拠として採用する必要性が高いことなども「特段の事情」に入れて良いでしょうか。
証拠の偏在を是正して挙証者の立証負担を軽減するというのが一般義務文書の趣旨なのだということを重視すれば、
証拠として採用する必要性も文書を開示すべき「特段の事情」に入れてよい、という筋はあり得るでしょう。
以 上

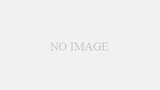
コメント