XはAを執拗に殴打し続け、Aは意識不明の重体になった。Xが去ったのち、たまたま通りかかったYがAの頭部を角材で数回殴打した。その後Aは死亡したが、検証の結果、Aの死因はXの殴打による傷害が原因であると判明し、Yの殴打による傷害は、Aの死亡を幾分か早めるに過ぎなかったことが分かった。XとYの罪責はどうなるか。
ロースクールに通っていると、法理論だけではなくて、答案の書きぶりについても勉強になるなあと思うことが少なくありません。
今日の刑法の授業でも、「法曹志望の腕の見せ所は当てはめだね」と聞きました。
今回は、危険の現実化説で因果関係を認定する際に、こういうワードを使ってみようと思ったものがあったので、共有します。
また、それに関連して授業で学んだこともお話しできたらと思います。
介在事情の異常性を「凌駕」し、危険が現実化した。
因果関係を検討する際に、実行行為と犯罪結果との間に何かしらの介在事情が絡むことによって、果たしてそれでも因果関係を肯定できるかという問題が浮上することがあります。
この問題に応えるべくして現れたのが「危険の現実化説」です。
介在事情が異常であればあるほど因果関係は否定される方向に傾くし、かたや実行行為に内包された結果発生への危険性が高ければ高いほど、因果関係は肯定される方向に傾きます。
上記の事例を検討するに、Xの殴打行為とAの死亡との間に因果関係があると言えるのでしょうか?
なぜならば、Yの殴打行為が間に挟まってきているからです。
そこでその疑問に答えるに、まず、Yの殴打行為という介在事情は異常と言えるでしょうか。
普通の人であれば、意識を失って倒れている人を見かけたらどうするでしょうか。
病院に連絡する人もいれば、あるいは見て見ぬふりをする人もいるでしょう。
ところが、Yは意識不明のAに暴行を加えており、これは異常も異常。
ゆえに、介在事情が異常であるため、いったんは因果関係が否定される方向に傾きそうです。
ところが、検証の結果、Aの死因は概ねXの暴行によるものでした。
Xの暴行は、Yの行為という介在事情をもってしてもなお、A死亡の結果を引き起こしたのです。
すると、やっぱり因果関係を認めるべきなのかな、という気がしてきます。
そこで、Xの危険性とYの異常性との優劣関係を分かりやすく伝えるフレーズとして紹介されたのが、「凌駕」という言葉。
「Xの暴行に内包された殺害の危険性は、Yの暴行という介在事情の異常性を凌駕し、A死亡という結果として現実化した。よって、Xの暴行とAの死亡との間には因果関係が認められる。」と論じる。
なるほど、何やらカッコイイ。
「死の二重評価」の誤解
因果関係も認められ、どうやらXには傷害致死罪が成立することになりそうです。
では、Yの罪責はどうなるのでしょうか。
例えば、甲が乙を車で轢いてしまい、乙は重傷を負ったとします。その後、乙を車に乗せて病院に運ぼうとした甲でしたが、乙は間もなく死んでしまうと思い直し、乙を山の中に捨てていったとしましょう。乙はその後、死亡しました。
このとき、甲には殺人罪の不真正不作為犯が成立することはさておき、車で轢いてしまったことについて業務上過失致死罪や、山中に置き去りにしたことについて保護責任者遺棄致死罪が成立するのでしょうか。
ここで登場するのが、「死の二重評価」はできない、というフレーズ。
死亡という結果は1つしか発生していないのに、殺人罪、業務上過失致死罪、保護責任者遺棄致死罪という3つの生命侵奪の責任を負うのは妥当でないですね。
ですから、死の二重評価、ならぬ、死の三重評価、はできない。
そういうわけで、乙には業務上過失傷害罪、保護責任者遺棄罪、そして殺人罪が成立することになります。
では話を戻して、意識不明のAの頭部を角材で殴打し、Aの死期を幾分か早めたYの罪責はどうなるでしょうか。
既にXには傷害致死罪が成立しており、A死亡の責任をXが負っています。
なので、Yには傷害罪が成立する、ということになるのでしょうか。
ここで注意することは、「死の二重評価はできない」とは、同一人物が死の責任を二重に負うことは妥当ではない、ということを意味しているということです。
したがって、Yの方はYの方でA死亡の責任を負うべきなのです。
Yには、ひとまず傷害致死罪まで認めてしまってよさそうです。
殺人の故意はそう簡単には認められない
ちなみに、Yに殺意まで認めることができるでしょうか。
殺人の故意があれば、傷害致死罪ではなく殺人罪を認めることができそうな事案なので、検討してみましょう。
教授曰く、生徒の答案を見てみると、殺意を簡単に認定してしまっていると感じるそう。
判例でも、被害者の髪を掴んで数十回壁に叩き付けた犯人に、殺意は認定されていないようです。
ですから、殺意を認定するにはしっかりと説得力持った形で論述する必要があるとのこと。
この記事の冒頭、当てはめは実務家志望の腕の見せ所だと言いました。
私ならこう書きますかねえ。
「Yは、Aの頭部という枢要部を目掛けて攻撃しており、手段としても角材を用いている。そのような行為を数回にわたって行えば、死亡する危険があることは認識し得たはずである。よって、Yは、Aが死亡しても構わないと思っていたと認められる。以上より、Yには殺人の故意がある。」
皆さんなら、どういう風に書くでしょうか。
以 上

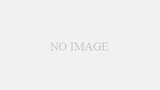
コメント