集会の自由を論じようとするとき、判例によって判断基準が違ったりするもんだから、一体どの判断基準をどんな時に使おうかと迷うことがありました。
とりあえず代表的な「泉佐野市民会館判決」のやつだけ覚えておくかあとか思っていた時期もありましたが、今回、ロースクールで集会の自由に関する授業を受けてきたので、その内容を共有していきたいと思います。
泉佐野市民会館判決
この事案は、ある過激な団体Xが、集会の用に供することを目的として設置・管理された施設である市民会館を、集会のために利用しようと思って申請したところ、これが拒否された事案です。
どのくらい過激な団体かと言えば、反対派グループと対立抗争を繰り返し、暴力沙汰、爆破事件を起こすほどです。今回のXの集会は、Xが掲げる「空港建設反対」運動の山場と目されており、Xにとっては非常に重要な集会だったでしょう。
市は、団体Xが集会を行えば「公の秩序をみだすおそれがある」と判断し、市民会館条例に基づいて申請拒否処分をしました。
判例では、まずもって当該市民会館が「公の施設」(地方自治法244条1項)に当たることを確認し、よって「正当な理由」なしに利用を拒否することはできない(同2項)から、当該市民会館の不当な理由による利用拒否は、集会の自由の実質的制限になりうることを確認します。
これらから、集会の自由を制限することができる場合というのは、施設の構造等から利用させるのが不相当である場合、利用者が競合した場合のほか、他の基本的人権が侵害されるなど公共の安全が損なわれる危険がある場合には必要かつ合理的な制限として集会の自由を制限できる旨述べ、利益衡量を示しました。
そして、集会の自由は経済的自由権よりも保障の程度は厚くすべき旨(二重の基準論)を述べて、これは利益衡量という緩やかな基準を厳しくしていると見えます。
上記に基づいて、地方自治法上の「正当な理由」を具体化した条例の要件、「公の秩序をみだすおそれがある場合」の解釈を判例は示します。
まず、集会の自由の制約は他の基本的人権との関係で制約される事がある旨を述べていましたから、「公の秩序をみだすおそれがある場合」というのは、集会の自由の重要性と比較して公共の安全が損なわれる危険性ゆえにこれを制約する必要性が優越する場合、を言うとして、利益衡量基準であるとの解釈をしめします。
ここまでであれば、裁判所の基本スタンスである利益衡量の基準という緩やかな審査基準で終わるところですが、上記の危険性については、明らかに差し迫った危険が具体的に予測できる場合であると言い、「公共の安全が損なわれる危険性」を認めるハードルを高く設定する事で、そう簡単には集会の自由の重要性と同じ天秤には乗っけないという形をとりました。審査基準を厳格にしたのです。
また、危険性の判断資料は、施設管理者の主観に限らず、客観的事情をも含めて判断するべきと言い、審査の密度も色濃い形に修正している格好です。
このように、利益衡量+明白な危険性基準+客観的事情という判断手法によって、泉佐野判決は結局、団体Xの利用申請拒否処分を合憲としました。
成田新法事件・暴走族追放条例事件
泉佐野判決のように利益衡量基準に加えていろいろなオプションをつけて審査の厳格度を挙げたのとことなり、利益衡量の基準のみを掲げた事件が成田新法事件です。
成田新法事件は、新空港開港に反対する暴力主義的な過激団体Yに対して、新空港の一定区域内における工作物の使用を禁止する処分をしたという事例です。
どれだけ過激化と言うと、新空港の開港に際して空港に侵入し、爆弾を投げ込むくらいに過激です。
処分根拠法は「多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供する」場合に使用禁止命令を出せるというもので、わりと適用対象が限定的である点も、ポイントの一つです。
さて、これによりYは、一定区域にて集会をすることができなくなったため、この事件でも集会の自由制約の合憲性が争われました。
ここで使われた判断基準は、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量するというもので、単純な利益衡量の基準が採用されています。
泉佐野判決のようなオプションも何もついてないですから、明らかにこちらの方が審査基準をしては緩いわけですが、なぜでしょうか。
これについて当時調査官だった千葉克己さんの解説では次のようなことを述べています。
価値優劣が明らかな事案でありしかも規制対象も限定的だから、裁判所の恣意が入り込む余地はあまりなくかつ利益衡量が困難であるという事情がないので、ほかに厳格な基準を持ってくる必要がない
団体Yという暴力団体の集会というのは果たして法的保護に値するかどうかすら怪しいのですから、本件における集会の自由の重要性の方は、公共の安全に劣ることが明らかです。そして、根拠法では「暴力主義的破壊活動者」に限定している点で、規制対象も限定的。
そういうわけで、単純な比較衡量で合憲判断したということです。
暴走族追放条例事件についても、猿払事件と成田新法事件とを挙げて、次のような判断基準を示しています。
規制目的の正当性、規制手段の合理性、規制によって得られる利益と失われる利益の衡量で判断する
どうやらこちらは、単純な比較衡量だけでなく、目的の正当性と手段の合理性というものも付け加えています。猿払事件の判断基準と同じような格好です。
では、猿払事件と並列して成田新法事件を挙げているのはなぜでしょうか。
高橋和之先生の本を見ると、猿払の目的審査と手段審査は形だけで、実際上は利益衡量で判断している旨を述べています。
この説に立つならば、結局のところは暴走族追放条例事件も成田新法事件と同じく、単純な利益衡量基準に則ったということなのでしょう。
実際、追放条例事件の調査官解説では、なぜ泉佐野判決のような厳格な審査基準を用いなかったのかについて、成田新法事件と全く同じ文言で説明されています。
たしかに、暴走族追放条例も、いわゆる暴走族、そしてこれに類似することが社会通念上認められる集団に対する規制でして、適用対象が限定的な事案でした。そして、彼らの集会というのは、周辺の飲食店の収入にも影響を与えるほど、周りの住民や観光客に威圧感を与えるものであったそうで、集会の自由の重要性はあまりなさそうな事案でもありました。
上尾市市民会館条例事件
以上みてきた事件は、みな、決して平穏な集会と呼べるようなものではありませんでした。
一方、平穏な集会のための施設利用について、申請拒否処分の合憲性が争われました事件もあります。
労働組合Zは、同組員幹部の合同葬を行う目的で、集会の用に供することを目的とする施設に利用を申請しました。
ところが、同組員の死亡の原因は、対立派閥による内輪揉めだったのではないかとの報道があったために、これでは住民に不安を与えるとして、上尾市は申請を拒否しました。
根拠法は、「会館の管理上支障があると認められるとき」には申請拒否処分をすることができるというものでした。
この事案では、泉佐野事件と同じように、上尾市市民会館は「公の施設」であるから、原則的には市民の施設利用を認めるべきであって、不当な拒否により集会の自由の実質的な制限にならないようにしなければならないことを言います。
ところが判断基準については利益衡量基準によらず、支障発生の事態が客観的な事実に照らして具体的に明らか予測される場合、には拒否処分をすることができると解釈しました。
泉佐野判決は、利益衡量基準に加えて、①危険性が明らかに差し迫っていること、②危険性が具体的に予測されること、③判断は客観的事情も入れること、を挙げました。
上尾市市民会館事件は、①支障発生が具体的に明らかに予測される場合、②判断は客観的事実に照らすこと、としており、支障発生が間近に迫っていることまでも要求されていません。
すると、泉佐野判決よりは緩やかな審査基準をとったことになるでしょう。
なぜでしょうか。
これについては、「公の秩序をみだすおそれがある場合」という公物警察作用と「施設の管理上支障がある場合」という公物管理作用が違いを生み出していると理解する見解があります。
そもそも、施設は管理権者の財産ですから、本来的には管理権者の裁量によって貸す貸さないを決めて良いもののはず。
ゆえに、公物管理作用は管理権者が本来的に有する権利なのです。
集会の自由も重要な権利ですが、これと天秤にかけられる公物管理権も強い権利だということになるので、それだけ審査基準も緩くなります。
泉佐野市民会館事件は、過激派団体の集会であったこともあり公物警察作用が適用されました。よって、解釈論も公物管理作用が中心となります。
上尾市市民会館事件は、内ゲバ事件が報じられていたという事情こそあったものの、集会の内容自体はお葬式であって、平穏な集会でした。ですから、公物管理作用の解釈論が問題となったのです。
よって、上尾市市民会館事件の方が、審査基準として緩くなったと言われています。
ちなみに、成田新法事件や暴走族追放条例事件のような単純な利益衡量基準と比べると、どちらが審査基準としては厳格なのでしょうか。
成田新法等は、過激な集会ではあったものの適用対象が限定的という事情がありました。
上尾市事件は、平穏な集会ではあったものの施設管理権という強い権利が天秤に乗ってきます。
一概にどうとは言えなさそうな気もしますが、上尾市市民会館事件が利益衡量基準をとっていないのは、そもそも「公の施設」での平穏な集会は拒否されるべきではないという価値判断があったように思われ、原則的には集会の自由の重要性の方が支障発生という不利益と比べて優越することが前提にあるからなのかなとも思いました(私見)。
そういうわけで、成田新法事件よりも、上尾市市民会館事件の方が審査基準としては緩いのかなと思いましたけど、これについて言及している基本書などあれば教えてください。
試験では何が問われそうか
ここまで、集会用に設置管理された施設や、公園・広場などの集会に適した場所に関する集会の自由の問題を見ていきました。これらは一般公衆の利用に供することを目的としている点で同一です。
かたや、一般公衆の利用に供することを目的とはしていない施設について、その利用を制約することはどうかという問題もあります(呉市学校施設目的外使用不許可事件)。
すると、まずもって一般公衆の利用に供する目的を有する場所か否か、ということを争点とする出題があり得そうです。
金沢市庁舎前広場事件(令和5年2月21日)は、9条を守ることを主張する護憲団体の市庁舎前にある広場の利用申請拒否処分が争われた事案ですが、そもそも市庁舎前の広場が市庁舎と一体的な広場なのか、そうではなく、市庁舎とは切り離された、一般公衆の利用に供する目的を有する広場なのかということについて判示がなされています。
ちなみに、もし、公務の用に供される場所であると認定するなら、「公の施設」ゆえに原則的には施設利用を認めるべきであって集会の自由の実質的制約にならないようにしなければならない、という論証は使えないことになる点は注意です。
根拠法は施設管理権に関する法令となっており、この点は上尾市市民会館事件と同じではあります。
しかし、金沢市庁舎前広場事件は「公の施設」ではありませんから、同じく施設管理権だからと言って、①支障の発生が具体的に明らかに認められる、②判断資料は客観的事実、という判断基準を採用はしていません。
金沢市庁舎前事件では、集会の自由の一般的な重要性(民主主義社会における重要な基本的人権として特に尊重されなければならない)と、反対の天秤に乗っかるものとしての公共の福祉を持ち出して、判断基準としては成田新法事件と全く同じ、単純な利益衡量基準で判断しています。
このような緩い基準を採用したのは、広場が公務の用に供する場所であること、それに伴って行政の政治的中立性が要求されること、施設管理作用であること、が影響したのかもしれません。
ちなみに、成田新法事件の事案に引き付けてみようとすると、まずもって、当該護憲団体が過激な団体であったとまでは言えないので、この点では成田新法事件の射程は及びそうもありません。
一方で、金沢市庁舎前事件では、「施設の管理上支障がある場合」を他の規定を参照してかなり限定的に解釈してはいて、その点では成田新法事件に近いです。
以下、その部分の解釈についての判決文
「特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的」による示威行為を禁止していることに照らすと、上記管理上の支障とは、被上告人の公務の用に供される庁舎等において威力又は気勢を他に示すなどして特定の政策、主義又は意見(以下「政策等」という。)を訴える示威行為が行われることにより、被上告人について、外見上の政治的中立性が損なわれ公務の円滑な遂行が確保されなくなるとの支障をいうものと解すべきである。
以 上

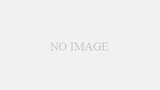
コメント