合憲限定解釈をすることによって、本来であれば違憲無効になりそうな法文も、無効とせずに運用させ続けることができる。
これが合憲限定解釈の意義であると言われています。
ただ、一方では、それは裁判所が改正法を制定するが如きであって、そもそも法は国会が制定するものであるというのに、これでええんか?という問題意識があります。
また、合憲限定解釈は、一見して法文からは読み取れない内容を認めることになるのですから、一般人からしてみれば不意打ちになるのではあるまいか?という問題意識もあるのですね。法文は明確であるべきで、また過渡広範でもいけないのです。
今回はそんな合憲限定解釈について、ロースクールで学んだ内容を参考に書いてみようと思います。
関係法令から合憲限定解釈
合憲限定解釈についての判例の一つ、広島市暴走族追放条例事件(最判平成19年9月18日)の概要は以下の通りです。
広島市暴走族追放条例では、「暴走族」とはいわゆる暴走族のほかに、「公共の場所において公衆に不安若しくは恐怖を与えるような特異な服装もしくは集団名を表示した服装で、い集、集会若しくは示威行為を行う団体」と定義されている。
そして、これら「暴走族」に当たる場合には、集会の中止命令をすることができ、これに従わない場合には犯罪行為になることが同条例で規定されている。
さて、暴走行為を日頃から行っている暴走族X、その面倒見であった甲は、広島市の広場にて暴走族Xの集会を行っていた。
市は、Xは「暴走族」に当たるとして集会の中止命令を出したが、Xはこれに従わなかったので、警察官は甲を現行犯逮捕した。
ここで甲側から主張されたのが、
条例が定義する「暴走族」というのは範囲が広すぎる、ゆえにこの条例は違憲無効、なので犯罪は成立しない
との主張でした。
たしかに、「公共の場所において公衆に不安若しくは恐怖を与えるような特異な服装もしくは集団名を表示した服装で、い集、集会若しくは示威行為を行う団体」というのでは、原発再稼働に反対する団体、性的マイノリティの権利を主張する団体、なんかも、これに当たりそうな雰囲気がしますよね。
これについて、判例は広島市暴走族追放条例全体の趣旨とその施行規則から、「暴走族」の範囲を次のように限定して解釈しました。
「暴走族」は、暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味での暴走族のほかには、服装、旗、言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団に限られる
ここでポイントなのは、法令から「暴走族」を限定解釈した点です。
法の明確性を重んじてした合憲限定解釈
一方で、「公安または風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」が不明確ではないかが争われた札幌税関検査事件(最判昭和59年12月12日)では、次のような要件を立てて、合憲限定解釈ができるかを判断しています。
表現の自由を規制する法律の規定を限定解釈することが許されるのは、その解釈により、①規制対象とそうでないものとが明確に区別することができ、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制対象となることが明らかにされる場合であり、また、②一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制対象となるかどうかの判断を可能ならしめる基準が規定から読み取ることができる
これは何を言っているのかと言うと、例えば「Aという法文からA’という解釈がされた」場合に、①はA’とA’でないものとを区別できるか、という話であり、②はAからA’が読み取れるのか、という話です。
そして、①を前半と後半で見てみると、前半部分「規制対象とそうでないものとが明確に区別することができ」の部分は、法の明確性の原則のことを言い、後半部分「合憲的に規制しうるもののみが規制対象となることが明らかにされる場合」というのは過渡広範ではないことを言っています。
このように、札幌税関検査事件の判断基準によると、単に関係法令から合憲的に解釈されればOKということではなく、明確性の原則や過渡広範になっていないかという観点も考慮に入れているのです。
答案の上では、暴走族追放条例事件のようにただ法解釈をするだけだと別に憲法答案って感じにならないので、札幌税関検査事件のように判断基準を挙げて論述した方が憲法答案っぽい気がします。
合憲限定解釈を主張できる者
ところで、追放条例事件では、典型的な暴走族Xの集会行為が問題になったわけですけど、裁判で争われたのは、「暴走族」の定義のうち、典型的な暴走族についての部分ではなく、「公共の場所において公衆に不安若しくは恐怖を与えるような特異な服装もしくは集団名を表示した服装で、い集、集会若しくは示威行為を行う団体」の明確性が争われたのです。
ぶっちゃけ、そこの明確性は、X側にとっては関係がない部分です。
それなのに、X側は不明確ゆえに違憲無効だと言えるのでしょうか。
これについては両説あるそうです。
まず、X側の主張を認めるべきであるとする説によると、法令全体が違憲無効になれば、Xの面倒見役である甲の犯罪は成立しないことになるという利益があるので、X側に関係のない部分の意見主張を認めるべきと言います。
一方、それって付随的違憲審査制に反していないか?とも思えます。
裁判所は、暴走族Xが条例でいうところの典型的な暴走族に当たるかどうかを判断すればよいのであって、それとは関係のない「公共の場所において公衆に不安若しくは恐怖を与えるような特異な服装もしくは集団名を表示した服装で、い集、集会若しくは示威行為を行う団体」について審判を加える必要がないからです。
皆さんは、どちらの説をとるでしょうか。
以 上

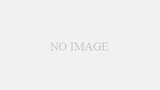
コメント