今回は、表見代理について、おもに本人を相続した無権代理人の追認拒絶権について、ローの授業で印象に残ったことを共有したいと思います。
資格併存説をとるべき理由
なぜ本人を無権代理人が相続したとき、追認拒絶権がなお無権代理人に認められるのか。
この問いについて、もし追認拒絶権が認められず、無権代理行為が当然に有効となってしまえば、それは相手方の取消権や無権代理責任の追及の余地を失わせてしまうから、という理由があげられます。
ところが、先生曰く、みんな答案でそのような理由を挙げてくるのだが、それは果たして決定的理由になるだろうか?とのこと。
確かに、相手方に取消権なり無権代理責任の追及の余地を与えるより、単純に無権代理行為が有効であるとしてみたところで、相手方の救済としてそこまで変わるものでもなさそう、と予習段階で思ってはいました。
では、本人を相続した無権代理人に追認拒絶権を認める決定的な理由とは何でしょうか?
まず、「相続」というのは包括承継しますよっていうだけのことなのに、なんで本人の資格と無権代理人の資格が融合して追認拒絶権ができなくなるのか、という点です。
つまり、資格融合説は「相続」という言葉と馴染まないというのが1点目。
また、無権代理人と相手方との間で交わされた無権代理行為の経緯が全く考慮されずに、画一的に追認拒絶権を認めないというのは、形式に過ぎるというのが2点目。
たとえば、無権代理人と相手方が、本人である被相続人の財産をちょろまかしてやろうとしたような場合には、相手方の信頼を保護してやる必要はないと言えます。
それなのに、無権代理人が本人を相続し、資格融合によって当然に無権代理行為が有効とされ、相手方が勝つというのは結論としてオカシイ。
これら2点が、資格併存説の決定的理由であるとおっしゃっていました。
無権代理人の相続人が更に本人を相続した場合の追認拒絶権
さて、資格融合説によれば、本人が有していた追認拒絶権は、相続によって無権代理人が有することになります。
このような無権代理人が、追認拒絶権を行使することができるかというと、それは矛盾挙動にあたるために信義則によって制限されるという判例(最判昭和37年4月20日)を私たちはよく知っているところです。
では、無権代理人の立場を相続した後、さらに本人の立場を相続した事例でも同じように矛盾挙動を持ち出すことってできるのでしょうか?
なぜならば、無権代理人の相続人は、相手方に対してなにもしていないのですから、その後本人の立場を相続して追認拒絶をしてみたところで、矛盾挙動は無いとも言えそうだからです。
同様の趣旨のことを、判例(最判昭和63年3月1日)の原審(名古屋高判昭和58年8月10日)が言っています。
原審は、昭和37年判例を「自らした」無権代理行為につき本人の資格において追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反するとしたものだ、と理解したのです。
従って、「自ら」無権代理行為を「していない」無権代理人の相続人については、昭和37年の射程に及ばず、むしろ本人が無権代理人を相続した場合と同視すべきと言いました。
しかし、昭和63年判例は「自らが無権代理行為をしていないからといって、これを別意に解すべき根拠はな」いと言い、原審を否定しました。
なぜそう理解したのでしょうか?
相続は包括承継です。なので、無権代理人の相続人でしかない者であっても、無権代理人と同視すべきだからです。
そのようなことを昭和63年は言っています。
確かに、追認拒絶権の行使が制限される根拠が、自らが矛盾挙動をしたから、と理解するとすれば、
本人が無権代理人を相続した場合には「追認を拒絶しても何ら信義に反するところはない」とも言った昭和37年判例の説示部分は、
本人が自ら矛盾挙動をしなかったから追認拒絶できるよ、という趣旨だと理解することになります。
しかし、無権代理人を相続した本人が追認拒絶をすることができるのは、もとより追認拒絶をすることができた立場だったからです。
さて、では矛盾挙動による追認拒絶権制限が無理だとすると、
無権代理人の相続人が、さらに本人を相続した事案である昭和63年判例は追認拒絶権を認めたのでしょうか?
昭和63年判例は、「無権代理人が本人を相続した場合と同様、履行義務を拒否できない」としました。
つまり、追認拒絶権は制限されると言いました。
どのような理屈で述べたのでしょか?
理由として判例は、無権代理人を相続した時点で、無権代理の責任としての履行義務を相続人は負っているわけであって、これにたまたま本人の立場を相続すれば履行拒絶できるというのは「偶然の事情によ」る「不測の利益を受ける」からと述べています。
つまり、矛盾挙動ではないにしろ、棚ぼた的利益を得る点が不当であるため、追認拒絶権を相続人は行使できないということです。
結局、自らが矛盾挙動をしたかどうかは、追認拒絶権の制限の一類型にはなるが、これだけが唯一ではないということです。
私は、独学で勉強していたとき、このような事例についても深く考えずに、矛盾挙動による追認拒絶権制限と論証してしまっていました。
独学だとこういうことに中々気づけないので、本当に助かりました。
以 上

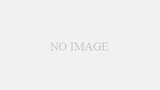
コメント